「ゴミ収集の仕事、正直もう限界かも…」そんな思いを抱えながら、今日も働いていませんか?早朝の出勤、重労働、悪天候の日も関係なく続く作業、さらには人間関係のストレス——「やめとけ」と言われる理由には、現場の過酷な現実が詰まっています。本記事では、ゴミ収集の仕事を辞めたいと感じる理由と向き合い方、そして後悔しない辞め方や次のキャリアの選び方までを、やさしく丁寧に解説していきます。
- ゴミ収集の仕事を辞めたくなる理由をリアルに紹介
- 実際に辞めた人の転職先や準備すべきことを解説
- 続けるか辞めるかの判断ポイントを丁寧に整理
- 退職前後に役立つ相談先・サポート手段も紹介
ゴミ収集の仕事を「やめとけ」と言われる理由とは?

「ゴミ収集の仕事はやめとけ」と言われる背景には、いくつかの共通した理由があります。ただの体力仕事だと思われがちですが、それだけではありません。早朝からの重労働に加え、悪天候の日も関係なく働き続ける過酷さ、人間関係の閉鎖性、そして世間からのイメージも関わっています。この章では、辞めたくなる3つの主な理由を詳しく解説します。
重労働で体力的にきつすぎる
ゴミ収集の現場は、見た目以上に体への負担が大きいです。特に民間委託や地方自治体の現場では、早朝5時台から出勤し、1日に何百件もの家庭ゴミを回収することも。作業中は常に立ちっぱなし、走り回りながらゴミを持ち上げ、積み込む動作の連続です。
特に夏は炎天下での作業、冬は凍える朝にゴミの中から出る汚水との戦いなど、過酷な環境が続きます。若いうちは耐えられても、年齢とともに身体に無理が効かなくなり「これを続けていくのは限界かも」と感じる人も少なくありません。
朝が早く、重いごみを何度も運ぶ日々
多くの作業所では朝5時台~6時台には出勤。通勤時間を含めると、実質4時台起きになることも。始業が早い分、退勤も早くはなりますが、生活リズムは乱れがちです。
さらに、一人あたりが処理するゴミの量は膨大で、1日に平均で数百キロを手作業で持ち運ぶケースもあります。例えば、マンションの大型ゴミステーションや商業施設から出る業務用ごみなどは、重さだけでなくサイズも不規則。中には液体の混ざった袋が破れ、体にかかることも日常茶飯事です。
こうした負荷が毎日続くと、腰痛やひざ痛などの慢性的な症状を訴える作業員も多く、「いくら給料が安定していても、体がもたない」と転職を考えるきっかけになります。
悪臭・汚れ・天候のストレスが大きい
ゴミ収集の仕事は、清潔さとは無縁の環境で行われます。特に真夏の生ゴミ、冷蔵庫の中身、排水が混じった袋など、想像を超える悪臭と遭遇することもしばしばです。臭いに敏感な人にとっては、毎日が地獄に感じることも。
また、汚れも避けられません。液漏れした袋や、虫が湧いているごみなどに直接触れる機会も多く、常に手袋・マスク着用が必須。中には服にまで染みついてしまうケースもあり、帰宅後すぐにシャワーを浴びる習慣がついている作業員も多いです。
さらに、雨でも雪でも回収作業は中止になりません。滑りやすい路面や視界の悪さのなか、安全を確保しながらごみを回収するのは想像以上に神経を使います。暑さや寒さが加わると体力的にも精神的にも消耗し、辞めたくなる気持ちが強くなるのは自然なことです。
夏の臭いや冬の寒さ、汚水など精神的負担も
夏の時期、生ゴミの腐敗は驚くほど早く進行します。炎天下で袋の中から漂ってくる臭気は、息をするのもつらいレベルになることも。回収車に乗っていても臭いは完全には防げず、車内にまで充満することもあります。
一方で冬は、手がかじかむ寒さの中でも素手に近い状態で作業をする場面もあり、水が手にかかるとひび割れやあかぎれが悪化しやすくなります。加えて、雨や雪が降る日には視界や足元も悪く、思わぬ事故のリスクも高まります。
こうした気温・天候・臭気・汚水といった複合的な負担が、精神面にじわじわと効いてきます。特に、慣れない新人や体調に波がある人にとっては「毎日が我慢の連続」であり、「もう続けられない…」と感じる一因となるのです。

人間関係が閉鎖的で合わないと辛い
ゴミ収集の仕事は、少人数の固定メンバーでチームを組んで行動することが多いため、人間関係がうまくいかないと一気に働きづらくなります。職場に馴染めなかったり、無言の圧力や暗黙のルールが多い現場では、精神的なストレスが溜まりやすくなります。
例えば、古株のベテランが仕切っているチームでは、明文化されていない「やり方」や「空気」が支配しており、新人や中途入社の人が意見を言いづらい雰囲気になっていることも。ミスや指示違いがあると、キツい言い方で注意される場面もあり、委縮してしまう人も少なくありません。
また、日中ずっと一緒に過ごす相手だからこそ、気が合わなかったときの居心地の悪さは深刻です。職場の人間関係がギスギスしていると、それだけで出勤するのが憂うつになってしまいます。いくら仕事内容に慣れてきても、人間関係のストレスがある限り「この仕事は無理だ」と感じてしまうのはごく自然なことです。
少人数チームゆえの空気や上下関係の難しさ
ゴミ収集の現場は、多くが2~3人の少人数体制。朝から夕方まで同じ車両・同じルート・同じ仲間と行動することになるため、ちょっとした相性の悪さが大きなストレスにつながります。たとえば、無口な人とずっと無言でいるのが苦痛だったり、逆に一方的に話しかけられ続けて疲れることもあります。
さらに、年功序列や慣習が根強い現場では、ベテランや年上の作業員の機嫌を損ねないよう気を使う必要も出てきます。明確なマニュアルがない分、「空気を読んで動け」といった暗黙のプレッシャーが強く、指示があいまいな中で動かなければならないことも。
このように、閉鎖的な人間関係の中で立ち回るのが苦手な人にとって、ゴミ収集という仕事は、肉体的なきつさよりも精神的な重さの方が大きく感じられることがあります。「職場の空気に馴染めない」「あの人と同じシフトは嫌だ」と思い始めたら、それは転職のサインかもしれません。

ゴミ収集を辞めたくなるときに考えるべきこと
「もう限界かも…」と思っても、すぐに辞める決断をするのは勇気がいりますよね。生活のこと、次の仕事、家族への説明──不安がいろいろ頭をよぎるはずです。この章では、辞めるか続けるか迷っている人が、冷静に判断できるようにするための視点をお伝えします。気持ちだけで動くのではなく、自分にとって本当に良い選択が何かを見極める時間にしてみましょう。
本当に辞めるべきか?まずは「なぜ辛いのか」を明確に
「辞めたい」と感じたとき、まずやってほしいのは「なぜそう感じているのか」を紙に書き出すことです。体力的に限界を感じているのか、人間関係が原因なのか、それとも単に仕事内容に飽きたのか──理由がはっきりすれば、改善できる可能性も見えてきます。
たとえば、「朝が早すぎるのが辛い」ということであれば、同業の中でも遅い時間帯のシフトを探すという方法もあります。「人間関係がきつい」というなら、職場や班を変えてもらえないか相談する余地があるかもしれません。
理由があいまいなまま辞めてしまうと、次の仕事でも同じような壁にぶつかってしまう可能性があります。まずは自分のストレスの根っこにあるものを正直に見つめ直すことが、最善の選択への第一歩です。
体力・人間関係・仕事内容…自分の限界を見極めよう
辞めるか続けるかを判断するには、自分が「どこまでなら耐えられるか」を知ることが重要です。人によって限界のポイントは違います。「腰に限界を感じている」「心が休まる時間がまったくない」「仕事内容が自分に合わない」──そんな具体的な感覚があるなら、それは大切なサインです。
逆に、「実はただ疲れてるだけで、もう少し休めば続けられそう」なら、休職制度の利用や有給を活用する選択も考えられます。自分の心と体が今、どういう状態なのか。無理して頑張る前に、一度立ち止まって確認してみてください。
「無理をして辞めることになるくらいなら、早めに判断して別の道に進んだ方が良かった」という声も多くあります。だからこそ、自分の限界と素直に向き合うことが、後悔しない選択につながるのです。

続ける価値があるか?将来のビジョンを考える
「今はきついけど、この先に何か見返りがあるかもしれない」──そんなふうに感じたことはありませんか?辞めるか続けるかを考えるうえで、「将来どうなりたいか」を描くことはとても大事です。ゴミ収集という仕事には、他の業種にはない安定性や役所との関係性といった強みもあります。
特に自治体の職員として勤務している場合、公務員に準ずる待遇を受けられるケースもあり、賞与や退職金、定年までの雇用継続などの恩恵があります。民間委託でも、地域によっては正社員登用があったり、給料が比較的高水準で安定している職場もあります。
「きついけど、やりがいがある」「自分にはこの仕事が向いてるかも」と思える瞬間が少しでもあるなら、一度将来のキャリアパスを洗い出してみましょう。長く続けた先にどんな可能性があるのか、イメージすることが判断材料になります。
安定収入や福利厚生などの利点も再確認
ゴミ収集の仕事には、他の業種に比べて「安定した収入が得られる」「雇用が途切れにくい」というメリットがあります。特に自治体が運営している場合は、雇い止めの心配が少なく、勤務年数に応じた昇給も見込めます。加えて、交通費支給・制服支給・社会保険完備といった福利厚生も整っているケースが多いです。
また、リストラのリスクが少なく、景気に左右されにくい業種の一つでもあります。感染症や不景気でもゴミは出続けるため、必要とされる職種としての需要は高く、家族を養っていくうえでの安心材料となることも。
もちろん「安定していても自分にとっての幸福とは限らない」と感じる人もいるでしょう。ただ、辞める前に今の職場の“プラス面”を整理してみると、「もう少し続けてみてもいいかな」と思えるきっかけになるかもしれません。
辞めたいと感じたときの選択肢と転職先候補
「ゴミ収集を辞めたいけど、次に何をすればいいか分からない」と悩んでいませんか?辞めたあとの道が見えていないと、不安でなかなか行動できないものです。でも実は、ゴミ収集の経験が活きる仕事もたくさんあるんです。この章では、実際に辞めた人が選んだ転職先や、体への負担が少なく社会貢献できる仕事などをご紹介します。

ゴミ収集を辞めた人が選んだ転職先とは?
ゴミ収集を辞めた人の多くは、体力面の負担を軽減することを重視して転職しています。たとえば、以下のような仕事が人気です。
- ビルメンテナンス(清掃)
- 工場の検品・軽作業
- 介護職(補助メイン)
- 福祉・NPO系の事務職
- 自治体関連の非正規事務職
体力不要な仕事や、社会貢献を実感できる職業へ
ビルメンテナンスや工場の軽作業は、室内で作業できることが多く、天候に左右されない点が大きなメリットです。また、ルーティン作業が中心で、慣れれば比較的楽に働けるという声もあります。
一方で、福祉系の仕事やNPO関連の事務職など、社会に役立っていることを実感できる仕事も人気です。特に「人の役に立っていると感じられる仕事がしたい」「感謝される場面がもっと欲しい」と感じる人には向いています。
また、自治体関連の窓口業務や非正規職員の募集も頻繁にあり、経験や年齢問わず応募できる案件も多く見られます。待遇や給与面ではゴミ収集に劣ることもありますが、心身への負担を考えると選ぶ価値は十分にあるでしょう。
転職前にやっておきたい準備とは
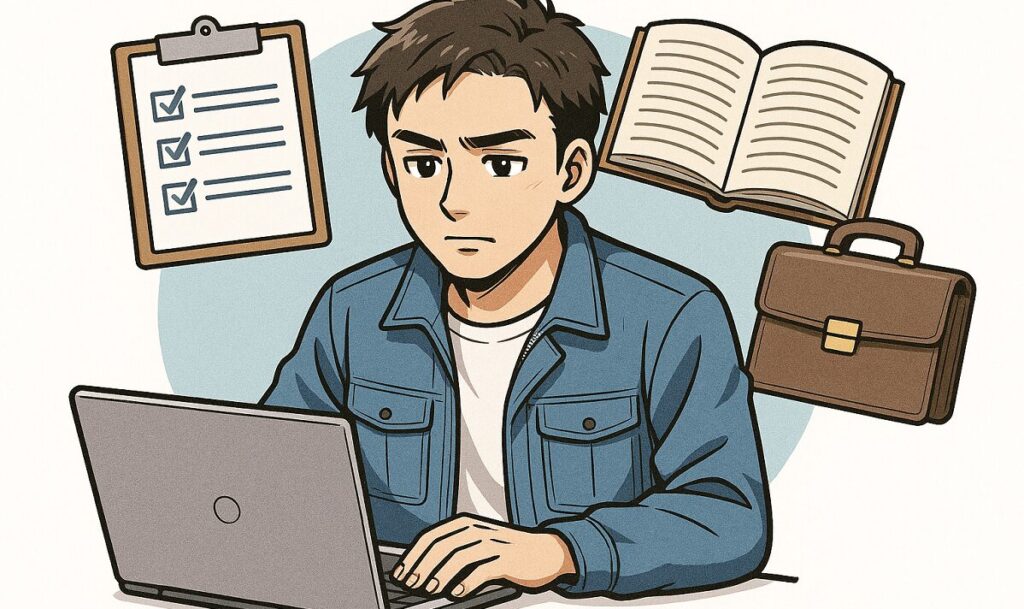
「辞めたい」と思ったとき、すぐに退職してしまうのも一つの手ではありますが、準備をしてから動くことで選べる選択肢がグッと広がります。特に転職活動は、情報を集めて、じっくりと自分に合う仕事を見つけることが重要です。勢いで辞めてしまってから「やっぱり前の方がマシだった」と後悔しないためにも、最低限の準備をしておきましょう。
準備というと大げさに聞こえるかもしれませんが、難しく考えなくて大丈夫です。次に紹介する3つのステップを踏むことで、気持ちにも余裕が生まれ、次に進む勇気も湧いてきます。
資格取得・自己分析・転職エージェントの活用
まずおすすめしたいのが、資格取得の検討です。たとえば「ビルクリーニング技能士」や「福祉用具専門相談員」などは、比較的短期間で取得可能でありながら、転職時に強いアピール材料になります。ハローワークでも無料の講座が開講されていることがあるので、ぜひチェックしてみてください。
次に、自己分析をしっかり行いましょう。これまでどんな仕事が楽しかったか、どんなときにストレスを感じたかを紙に書き出すだけでも、自分に合った仕事のヒントが見つかります。「黙々と作業したい」「人と話すのが苦手」など、自分の得意不得意を把握することがミスマッチを防ぐカギになります。
さらに、転職エージェントを活用するのも有効です。登録無料で非公開求人を紹介してもらえるうえに、履歴書の添削や面接対策のサポートも受けられます。特に「どこが自分に合っているか分からない」と感じている人には、客観的な意見がもらえる場として心強い味方になってくれます。
辞めたいときに相談すべき相手とサポート方法

「もう無理…」と感じたとき、心の中に抱え込んだままだと、ますますしんどくなってしまいます。そんなときこそ、信頼できる誰かに相談することがとても大切。自分の状況を言葉にするだけでも、気持ちが整理されていくからです。ここでは、社内で相談できる人、そして外部で頼れるサービスについてご紹介します。

社内の信頼できる人に相談してみる
もし、職場に「話しやすい」と思える上司や同僚がいるなら、まずはその人に現状を伝えてみましょう。ポイントは、「愚痴」ではなく「相談」として話すことです。たとえば「今、少し体力的にしんどくて…」といった切り口で話せば、相手も前向きに耳を傾けてくれるはずです。
部署やチームを変えてもらう、シフトの時間帯を見直してもらうなど、思いがけない配慮が得られることもあります。特に公務系の現場では、労働組合や福利厚生担当の窓口もあるので、個別に相談してみると解決の糸口が見つかるかもしれません。
もちろん、誰にも言えずに辞めたい気持ちを抱えている人も多いと思います。でも、誰か一人でも「味方」がいるだけで、精神的な負担はかなり軽くなります。無理せず、信頼できる相手に少しずつ話してみることをおすすめします。
外部サービス(退職代行・転職支援)の活用も視野に
どうしても社内では相談できない、もう職場に行くのも辛い…という場合には、外部サービスを頼るのも一つの手です。最近では「退職代行サービス」も広く知られるようになり、LINEやメールで相談しながら、会社とのやり取りを代行してくれる仕組みも充実しています。
特に、人間関係のトラブルやハラスメントが理由で辞めたいときには、直接話し合うよりもこうした第三者のサポートを通したほうがスムーズなケースが多いです。また、転職支援サービスでは、職歴や希望条件をもとに新たな仕事を探してくれるため、次に向けての一歩を効率的に踏み出せます。
「逃げるのは悪いこと」と思わなくて大丈夫です。自分を守るために頼れるものは、積極的に使っていいんです。環境を変えることで心がラクになり、次の道で輝ける自分に出会えるかもしれません。
Q&A:ゴミ収集の仕事でよくある悩み
- ゴミ収集の仕事は本当にそんなにきついの?
-
はい。ごみの重量や天候に関係なく作業があること、悪臭や汚れなど精神的にきつい要素も多く、実際に辞めていく人も少なくありません。ただ、職場や地域によってきつさの度合いは異なるので、見極めも大切です。
- 辞めたいと思ったとき、まず何をすべき?
-
いきなり辞めるのではなく、まず「なぜ辞めたいのか」を整理することが大切です。そのうえで社内相談や環境の見直し、転職準備など、段階的に動くことで後悔の少ない選択ができます。
- 転職するならどんな仕事が向いている?
-
体力的な負担が少ない仕事や、社会貢献を実感できる仕事が選ばれやすいです。ビルメンテナンスや軽作業、福祉系の仕事、自治体関係の非正規職員などが転職先の例として多く挙げられます。

ここまで読んでくださってありがとうございます。ゴミ収集の仕事は本当に尊い仕事ですが、無理して続ける必要はありません。あなた自身の体と心が一番大事。辞めたいと思ったら、自分を責めずに、ちゃんと向き合ってあげてくださいね。

コメント